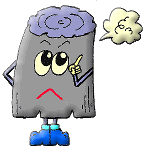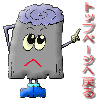【木炭を利用した水質浄化装置】◆特許/第3150947号◆
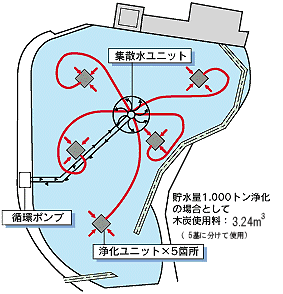
【現在の水質汚染問題】
生活排水の多様化、農薬の使用、科学物質の排出等の影響により、湖沼、河川ため池等の水質が著しく悪化しています。
特に夏場になると水質の富栄養化によりアオコが大量に発生し、これが更に水質汚染を助長する結果となっています。
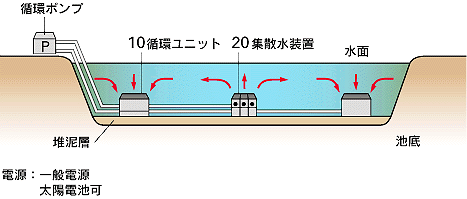
アオコは動物の動きを鈍くし、ひどくなるとマヒなどにより死に至らしめることが報告されています。これは、主として神経毒としてのアルカロイド、また、肝臓毒としての環状ペプチドが原因とされています。また、水道水の水源とされる河川や湖沼の水には、リンや窒素等による植物プランクトンや放射菌が異常に繁殖し、これらの微生物はカビ臭の原因ともなっている。
このような悪化した水質を改善する方法として、木炭を濾過材に使用し、木炭に活着する自然の微生物の働きで汚濁水の浄化をおこなう下記システムが有効です。
このシステムはトヨタ自動車㈱の「トヨタの森」計画の吉田池の水質浄化システムとして採用され、汚濁水質を生態系の豊かな水質に転換しています。


水質改善前(吉田池)
貯水量1000トン
木炭による水質浄化
1ヶ月経過後
木炭で一定の厚さの層を形成し、浄化する水を一定の流速で通過させ微生物の吸着分解能力により水質を浄化します。
☆この浄化法で使用される木炭は、原料が広葉樹(おもに楢炭)で炭化温度が700℃以上のものを使用します。
①まず最初に微生物による物質転換(吸着・分解)が行われ、ついで微生物の増殖と共生環境が作られます。
③さらに、木炭層による水の浄化を開始してから数週間後には微生物も加わって食物連鎖が除々に進み、木炭層内で水の浄化が持続されます。
このような、微生物による物質転換を持続させるためには木炭層内を通過させる
汚染水の流速を汚染の程度に応じて調整しなければなりません。
汚染水の流速が早すぎると水の木炭との接触速度が速すぎて効果が期待できませんので、このシステムは汚染の程度に応じて流速をコントロールできることを特徴としています。
このシステムは河川、湖沼の汚染指標である6項目(DO,SS,COD,BODT-P)に有意な改善が観察されました。
また、工場排水、生活雑排水、農業用水、排水等が複雑に絡み合っている複合汚染の浄化に威力を発揮します。